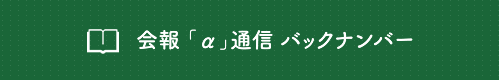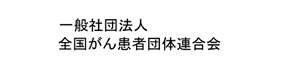生きている人間としてあなたと出会いたい
生・老・病・死は“自分ごと”。がん体験から生命(いのち)を見つめる。
がん患者や、体験者、家族、まわりの人々が、語りあい、分かちあい、学びあいながら、
最後まで自分らしく生きることをめざし、ともに支えあう会です。
活動に関するお知らせ
新着情報
|
NEW2024.4 .11
|
【αサロン開催のご案内】 桜の季節となりました。 久しぶりの青空に、桜が映えるなぁと感じています。支えあう会αでは、毎月第一日曜日と第三水曜日にサロンを開催しています。 第三水曜日は、ZOOM使用によるWebサロンとなります。今年度より試験的に第三水曜日は夜間(20:00~21:00)の開催となっています。 お時間に間違えのない様にお願い致します。 (スタッフ:土田) サロン開催日:4月17日(水)20時00分~21時00分 (ZOOMによるWebサロンです) お申込みは、こちらをクリック
|
|---|---|
|
NEW2024.3.4 |
【千葉市:アピアランス支援】 千葉市では、がんに患された方が治療を続けながら仕事や社会参加が継続出来る様に補正具などの費用の一部を助成することになりました。 詳しくはこちらをクリック |
|
2024.01.09 |
【α2023年度連続講座 開催のお知らせ】終了 Webと対面によるハイブリッド開催になります。 ・第二回 2024年2月4日(日) がん治療と栄養 ~食べて治す~ 【講師】鍋谷 圭宏さん
千葉県がんセンター副病院長/食道・胃腸科科 外科部長/日本臨床栄養代謝学会副理事長 がんと闘うには、体力もなければいけません。 また、それぞれの治療後にどの様な食事をしたら良いのかなど疑問を聞いてみましょう。 参加申し込みはこちらをクリック |
| 2024年【賀正】 |
本年もよろしくお願い致します。
|
| 【医療従事者向け】 |
医療情報誌 ナースマガジン 2023 Summer 「生きる」を支えるがん看護 APC・アピアランスケア・マギーズ東京 他 出典:メディアバンクス株式会社(協力:栗原医療器械店) 医療従事者の方は、こちらをクリック |
|
2023.8.16 |
【千葉県がん患者大集合2023 開催のお知らせ】 11月5日(日)Webと対面によるハイブリッドによる千葉県がん患者団大集合を開催致します。千葉県、各市、各病院、各医師会、企業、各患者会の協力の元、医師による講演があります。 終了致しました。 編集後 千葉県がん患者団体連絡協議会のホームページにて 視聴のURLをお知らせ致します。 千葉県がん患者団体連絡協議会のホームページはこちら |
|
2023.7.19 |
【バックナンバー】α通信 No.85号 「膵がん教室」 ~支えあう会「α」版~ 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科科長 奥坂拓志さん |
|
2023.6.20 |
【バックナンバー】 α通信 No.87号「プレシジョンメディション」と「がんゲノム医療」を学ぼう 北里大学病院集学的がんセンター 佐々木治一郎さん |
|
2023.6.20 |
【バックナンバー】 α通信 No.89号 がんになって悩むこと ~心のケア・緩和医療の視点から~ 都立駒込病院 精神腫瘍科 秋月伸哉さん |
|
2023.6.13 |
【バックナンバー】 α通信 No.84号 放射線治療 あなたのイメージ合っていますか 国立がん研究研究センター東病院 全田貞幹さん |
新型コロナウイルス禍における「α」の活動について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置を受けて、2020年から2022年とWebでの活動を中心に、形態や回数などを模索してきました。新型コロナウイルス感染症の生活への影響はまだまだ続いていますが、2023年度は、Webと並行して、徐々に対面サロンや連続講座を復活させていきたいと考えています。
今後、状況の変化によって、変更することも予想されますが、その際は、ホームページ、メール、郵便などでお知らせします。
2023年度 年間活動予定
NPO法人支えあう会「α」は、すべてがんの患者さん、ご家族を対象として活動しているがんの患者会です。
患者さんやご家族の交流の場の提供、がんに関する情報提供など、様々な活動をしています。
これらの活動は一部を除き、会員以外の一般の方もご参加いただけます。お気軽にご参加、お問い合わせください。
4月
|
2日(日) |
「α」サロン(対面・Web) |
|---|---|
| 8日(土) | 気功教室 |
| 19日(水) | サロン(Web) |
| 22日(土) | 気功教室 |
5月
| 7日(日) | 「α」サロン(対面・Web) |
|---|---|
| 13日(土) | 気功教室 |
| 17日(水) |
サロン(Web) |
| 27日(土) | 気功教室 |
6月
| 4日(日) | 総会(Web) |
|---|---|
| 10日(土) | 気功教室 |
| 21日(水) |
サロン(Web) |
| 24日(土) | 気功教室 |
7月
| 2日(日) | 部位別サロン・血液がん「α」(対面・Web) |
|---|---|
| 8日(土) | 気功教室 |
| 19日(水) | サロン(Web) |
| 22日(土) | 気功教室 |
8月
| 6日(日) | 遺族サロン(対面・Web) |
|---|---|
| 12日(土) | 気功教室【中止となりました】 |
| 26日(土) | 気功教室 |
| 注 意 | 第3水曜日のサロンはお休みです。 |
9月
| 3日(日) | 部位別サロン・泌尿器がん(前立腺含む(対面・Web) |
|---|---|
| 9日(土) | 気功教室 |
| 20日(水) | サロン(Web) |
| 23日(土) | 気功教室 |
| 注 意 | 23日(土)は、祝日のため開催は検討中です。 |
10月
| 1日(日) | 連続講座またはサロン |
|---|---|
| 14日(土) | 気功教室 |
| 18日(水) | サロン(Web) |
| 28日(土) | 気功教室 |
11月
| 5日(日) | 部位別サロン・頭頚部がん(対面・Web)※日程変更になります |
|---|---|
| 11日(土) | 気功教室 |
| 15日(水) | サロン(対面・Web) |
| 25日(土) | 気功教室(対面・Web) |
12月
| 3日(日) | 部位別サロン・肺がん(対面・Web) |
|---|---|
| 9日(土) | 気功教室 |
| 20日(水) | サロン(Web) |
| 23日(土) | 気功教室 |
1月
| 7日(日) | 新年会またはサロン(対面・Web) |
|---|---|
| 13日(土) | 気功教室 |
| 17日(水) | サロン(Web) |
| 27日(土) | 気功教室 |
2月
| 4日(日) | 連続講座またはサロン |
|---|---|
| 10(土) | 気功教室 |
| 21日(水) | サロン(Web) |
| 24日(土) | 気功教室 |
3月
| 4日(日) | 部位別サロン・胃・食道・大腸がん(対面・Web) |
|---|---|
| 9日(土) | 気功教室 |
| 20日(水) | サロン(Web) |
| 23日(土) | 気功教室 |
入会をご希望の方へ
支えあう会「α」では、会員・賛助会員を募集しています。
会員は各種サロンや定位例会が無料になり、どなたでもご参加いただけます。